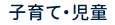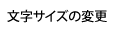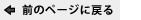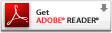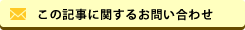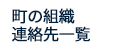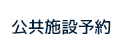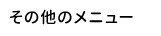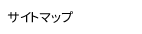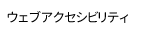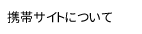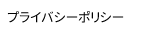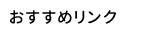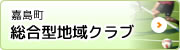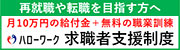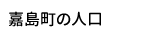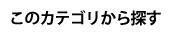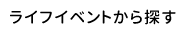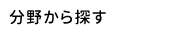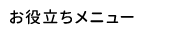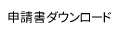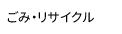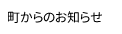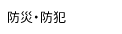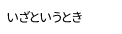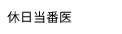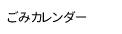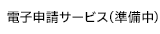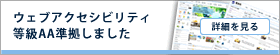固定資産税
固定資産に係る各種届出や申告に関してはこちらです→固定資産に係る各種届出、申告書
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税の税額通知・納付書
固定資産税の税額通知・納付書は毎年5月上旬までに発送されます。
固定資産税の課税標準額が免税点未満で税額がかからない方には発送されません。
5月半ば以降過ぎても税額通知・納付書が届かない方は税務課までお問い合わせください。。
住所を変更された場合正しく税額通知が発送できない場合がありますので、お手数ですがお下記より手続きをお願いいたします。
納税義務者
原則として、毎年1月1日(賦課期日)において、町内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。
土地 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
納税義務者が死亡された場合
土地・家屋・償却資産の所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には賦課期日現在で、その土地・家屋・償却資産を現に所有している人が(相続人等)納税義務者を引き継ぐことになります。(正式な名義変更は、法務局での手続きになります)
その手続きがお済みでない場合は、「相続人代表者指定届出書兼固定資産税現所有者申告書」により相続人の代表者、地方税法第384条の3に規定する「現に所有する者」を決めていただき、その届に基づいて、その代表者に納税通知書等を送付します。
相続人代表者指定届出書兼固定資産税現所有者申告書(PDF 約70KB)
※固定資産の「現所有者(相続人等)申告」の制度化について(令和3年1月1日から適用)
令和2年10月1日から、令和2年度税制改正によって、地方税法第384条の3及び嘉島町税条例第74条の3の規定に基づき、現所有者は町に申告する義務が生じることとなりました。
納税管理人
納税義務者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)が無い場合は、納税管理人を指定することができます。
納税管理人の指定が必要となった日から10日以内に、納税管理人の住所が嘉島町内の場合は納税管理人申告書を、納税管理人の住所が嘉島町外の場合は、納税管理人承認申請書を提出してください。
確認後、その納税管理人に納税通知書等を送付します。
納税管理人申告書・納税管理人承認申請書(PDF 約30KB)
納税管理人の解除を行う場合
納税管理人(解除)申告書・納税管理人承認申請書(PDF 約31KB)
納税管理人の変更を行う場合
納税管理人(変更)申告書・納税管理人承認申請書(PDF 約31KB)
固定資産の種類、価格
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。土地
固定資産評価基準によって売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目は、宅地、田、及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
家屋
家屋の評価は固定資産評価基準によって再建築価格を基準とする方法によって求めます。家屋の評価は基準年度(3年ごと)に評価替えが行われますが、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、引き上げることなく、前年度の評価額に据え置かれます。
| 評価額 | = | 評点数 | × |
評点一点当たりの価額 (木造0.99、非木造1.1) |
||
| 評点数 | = | 再建築費評点数 | × |
損耗の状況 による減点補正率 |
× | 需給事情による減点補正率 |
再建築費評点数
1 新築、または増築して1年度目
実際に物件を現地確認し、固定資産評価基準に従って評価します。
再建築費評点数 = 標準評点数 × 補正係数 × 計算単位の数値
2 新築、または増築して2年度目以降
|
再建築費評点数
|
=
|
基準年度の前年度における 再建築費評点数
|
×
|
再建築費評点補正率 令和3年度 木造 1.04 非木造 1.07 |
償却資産
固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮して計算します。
【申告が必要な方】
会社や個人で工場や商店を経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けている方、農業をされている方など
事業を行っている方で、1月1日現在に嘉島町内に償却資産を有している方
償却資産の申告
上記、【申告が必要な方】に該当する場合、毎年1月31日までに嘉島町税務課に下記様式にて固定資産税(償却資産)の申告をお願いいたします。前年と資産の状況が変わっていない場合でも申告は必要になります。
固定資産の特例
固定資産の特例に該当する場合、申請書の提出が必要になります。
認定長期優良(200年)住宅にかかる固定資産税減額申告書(PDF 約77KB)
住宅用地の特例
住宅が建っている土地(住宅用地)はその面積の広さによって、小規模住宅用地、一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)にかかる課税標準額について、その価格を1/6とします。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地に係る課税標準額について、その価格を1/3とします。
住宅用地の範囲
住宅用地には次の二つがあります。
1 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
・・・家屋の床面積の10倍まで
2 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
・・・その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に下表の一定の率を乗じて得た面積まで
| 家屋の種類 | 居住部分の割合 | 一定の率 | |
| 1、2 | 以外の併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
| 1/2以上 | 1.0 | ||
| 2 | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
| 1/2以上3/4未満 | 0.75 | ||
| 3/4以上 | 0.75 |
新築家屋の軽減
新築された住宅については、新築後一定期間固定資産税額が減額されます。
新築住宅の要件
1 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については居住部の割合が1/2以上のものに限られます。
2 床面積要件・・・50平方メートル以上280平方メートル以下
※一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル以上
※分譲マンションなどの区分所有家屋、独立的に区画された賃貸マンション、2世帯住宅などの場合、「専用部分の床面積+持ち分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
減額される範囲、減額の割合
減額の対象は、新築された住宅用家屋のうち居住部分だけであり、併用住宅の店舗、事務所、倉庫部分などは対象外です。また、居住用部分の床面積のうち120平方メートルまでが減額の対象です。
減額対象に相当する固定資産税額の1/2が減額されます。
減額される期間
一般住宅・・・・・・新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅棟は5年度分)
長期優良住宅分・・・ 新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅棟は7年度分)
住宅をリフォームした場合の減税制度
適用要件を満たすリフォームを行った場合申告手続きを行うと、工事を行った翌年分の当該家屋に係る固定資産税の減額を受けることができます。
住宅リフォームによる減税措置の詳細などについては、下記もあわせてご覧ください。
「リフォームの減税制度(平成29年10月発行)」((一社)住宅リフォーム推進協議会HP)
対象となる工事
◎耐震・・・家屋面積120平方メートル相当まで、固定資産税額の1/2
◎バリアフリー・・・家屋面積100平方メートル相当まで、固定資産税額の1/3
◎省エネ・・・家屋面積120平方メートルまで固定資産税額の1/3
◎長期優良住宅化・・・家屋面積120平方メートルまで固定資産税額の2/3
申告期間
工事完了後3か月以内(やむを得ない場合を除く)
提出書類
固定資産の非課税
地方税法第348条第2項の規定により非課税となる固定資産があります
例)宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物および境内地
学校法人等が設置する学校において、直接保育または教育の用に供する固定資産
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等の政令で定められた社会福祉事業の用に供する固定資産
例以外の固定資産について、非課税に該当するかは上記の法令で確認いただくか、嘉島町税務課にお問い合わせください。
地方税法第348条第2項に規定する非課税の適用を受ける場合は下記書類をご提出ください。
固定資産の減免
嘉島町税条例第71条の規定により、下記に該当する固定資産のうち、町長において必要があると認めるものについては減免を受けることができます。
1)貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
2)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
3)町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
4)その他特別の事情があるものの所有する固定資産
減免を受けようとする場合、減免申請書を提出してください。
追加情報
この記事には外部リンクが含まれています。
カテゴリ内 他の記事
- 2022年3月16日 個人町民税・県民税(住民税)の申告について
- 2025年12月1日 給与支払報告書提出のお願い
- 2025年4月1日 令和7年度 町税等納期について
- 2025年4月1日 軽自動車税
- 2025年4月1日 国民健康保険税の算出
- 2022年11月16日 固定資産に係る各種届出、申告書
- 2024年5月10日 個人町民税
- 2023年12月28日 産前産後期間に係る国民健康保険税の免除について
- 2023年8月9日 熊本地震に係る固定資産税等についてのおしらせ
- 2022年12月13日 令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が始まります...